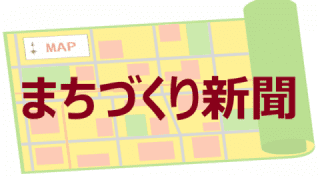理事長鶴岡 近況報告
桃の花 あずさやかいじで 往復し
自立に向けて 制度交渉し
むらさき(2025年3月)
「制度交渉し」 理事長 鶴岡和代
2025-04-01
みなさんお元気でしょうか。
春のような陽気になったり雪が降ったりするような気候で体がなかなかついていかない今日です。
テレビのニュースで桃の花が咲いているのを観て、40年前を思い出しました。
昭和63年に山梨県にある麦の家という養護施設に入所しました。
1週間後には東京に帰ってきて、そこから私の人生が変わりました。
桃の花は私にとって自立への輝きでした。
入所しながら月1回特急電車のあずさやかいじに乗って東京-山梨間を往復する日々になりました。
桜よりも桃の花はピンクが濃くて一面桃畑で、空もピンクに見えるような感じでした。
施設にいながら東京の厚生省や東京都に仲間と出向いて施設の問題点や4人部屋から1人部屋にできないかという交渉までやっていました。
その傍ら、実家がある台東区で自立生活がしたいと思い、仲間と制度交渉しました。
その頃は制度自体も少なかったので、自立生活をするなんてボランティアを集めて暮らす以外に方法なんてなかったのです。
今は重度訪問介護という制度があって、必要によって介助がつけられるようになりました。
テレビのニュースで賃上げの問題を話している場面があり、介助者から「理事長、TSTも賃上げしてくれませんか。」と言われましたが、私たちの介護制度の金額が上がらないと賃上げも難しいのです。
桃の花を思い出すと、仲間と一緒に私たちの介護制度を交渉してきた頃を思い出します。
そして、ボランティアも一緒に巻き込んで交渉した頃の思い出も蘇ります。
今は介助派遣というかたちになっているので、交渉というよりは必要な介護時間を相談員という人と共に必要な時間を交渉する感じで、障がい者が団体を組んでやるような交渉は難しい状況にあります。
世の中の賃上げが難しい中で更に福祉制度の金額を上げるのは難しいのです。
空一面にピンクで埋め尽くす桃の花は、こらからも交渉していかないとなかなか咲かない花です。
みなさんも一度山梨の桃の花を見てみてください。
「施設と地域の暮らし」 理事長 鶴岡和代
2025-03-01
皆さんお元気ですか?
2月半ばになっても寒い日が多いです。
いつになったら春になるのかな。
待ち遠しいですね。
さて、TSTの利用者でもあり、CILの日中活動の仲間でもあった新橋三枝子さんが1月17日に天国に召されました。
今頃、空の上から私たちを見守ってくれていることでしょう。
私と新橋さんの出会いについて今回は書きたいと思います。
私は、昭和63年11月に山梨県にある「麦の家」という療護施設に入所しました。
地域で暮らせない人が入所する施設です。新橋さんは、私が入所して半年ぐらい後に入所しました。
お部屋が別だったのでたくさん話をした記録があんまりないのですが、夜7時くらいから、4,5人で食堂に集まってお酒を飲んだり、話をすることがありました。
その仲間の1人でした。
私は入所してから半月ぐらいで、生活指導員の畠山さんから「東京に帰りたいか」と聞かれて、「帰りたい」と言ったら、「僕の言うことも聞いてくれるか」と聞かれて、ドキッとしました。
そして、清瀬療護園に入園している太田さんと出会うことになりました。
太田さんの話を聞いていて、私も自立生活を夢見るようになって、山梨と東京を半月に1回往復するようになりました。
東京都や厚生省に出向いて、施設改善や1人部屋の要望などを交渉したり、勉強など行う集まりに私も加わって、太田さんと一緒に活動してました。
そして、「麦の家」のみんなに報告書をまとめて配りました。
そういう姿を新橋さんが見ていて、「鶴岡さんみたいにできないな」と言われました。
そして、私が平成2年に「麦の家」を退所して、今の自立生活になりました。
平成8年4月に「CILたいとう」を立ち上げて、その後、新橋さんが私を追いかけるように「CILたいとう」に来て、自立生活をしたいと言いました。
「自立生活はいろんなことで大変だから麦の家にいたほうがいいんじゃないの」って言った覚えがあります。
私も自立したいと思ったときに八王子の「ヒューマンケア協会」に相談に行ったら、「施設にいたほうがいいんじゃないの」と言われた記憶があります。
でも自立して、新橋さんも自立して、地域の暮らしをしています。
いろんなことがあるけれど、新橋さんは地域の暮らしで幸せだったのかと思ったりしました。
私の介助者が交代する時に、必ず新橋さんの話をするのを聞いていて、幸せだったんだと実感しました。
そして、愛しまれて羨ましいなと思ったりもしています。きっと今頃、「鶴岡さんよりも幸せだったよ」と言っているような気がします。
これからも私たちのことを見守っていてください。
「機能低下」 理事長 鶴岡和代
2025-02-01
1月半ばになって寒い日もあれば春のようなあったかい日もあります。
みなさんお元気でしょうか。
今年の目標に向かって歩んでいる人もいれば、目標を立てても歩みだせない人もいると思います。
私も目標は立てているけれど、それに向かって歩むのができない日もあります。
さて、今日は私の話をします。
昭和25年7月25日の生まれで、後期高齢者の仲間入りをします。
生まれつき脳性麻痺で、8歳から17歳まで小平にある整育園に入園し、機能訓練と生活指導を受けて身の回りのことは自分でできるようになりました。
歩くこともできるようになり3cmくらいのヒールがある靴を履いて、ユニークダンスという名前の集まりがあって社交ダンスのような遊びもやっていました。
35歳の頃から首の骨が圧迫される変形性頚椎症と診断されて、だんだんと機能低下をして昭和63年に山梨県の麦の家という施設に入所することになってしまいました。
私たちは年齢を共に機能低下をすると先輩たちから言われていて、そうそう私もそうなってしまったかと思い、姥捨て山に行くような思いでした。
麦の家に入所して3日目で自立生活を目指すことになって、先輩たちの話を聞いたり、先輩の家に行って生活状況を観たりして、3日生きればいいやと思って自立しました。
その後もいろいろ機能低下はあったんだけど、6年前の気管切開を経て人工呼吸器をつけて暮らしています。
カニューレ交換のときは、痛さと不安で毎回笑えないです。
日々介助者と訪問看護師に医療ケアを受けて暮らしています。
振り返ってみれば、機能低下を認められず過ごした日もありました。
でも、友だちに励まされ支えられ、仲間にめぐり逢い今日に至っています。
健常者でも体力の衰えを認めたくないと言っていたので、私だけじゃないんだと思う毎日です。
新しい年になってこんなことを書くのはなんだかなと思いましたが、自分のことを自分で認めるっていうのは難しいことだなと思ったので書きました。
みなさんお元気でしょうか。
今年の目標に向かって歩んでいる人もいれば、目標を立てても歩みだせない人もいると思います。
私も目標は立てているけれど、それに向かって歩むのができない日もあります。
さて、今日は私の話をします。
昭和25年7月25日の生まれで、後期高齢者の仲間入りをします。
生まれつき脳性麻痺で、8歳から17歳まで小平にある整育園に入園し、機能訓練と生活指導を受けて身の回りのことは自分でできるようになりました。
歩くこともできるようになり3cmくらいのヒールがある靴を履いて、ユニークダンスという名前の集まりがあって社交ダンスのような遊びもやっていました。
35歳の頃から首の骨が圧迫される変形性頚椎症と診断されて、だんだんと機能低下をして昭和63年に山梨県の麦の家という施設に入所することになってしまいました。
私たちは年齢を共に機能低下をすると先輩たちから言われていて、そうそう私もそうなってしまったかと思い、姥捨て山に行くような思いでした。
麦の家に入所して3日目で自立生活を目指すことになって、先輩たちの話を聞いたり、先輩の家に行って生活状況を観たりして、3日生きればいいやと思って自立しました。
その後もいろいろ機能低下はあったんだけど、6年前の気管切開を経て人工呼吸器をつけて暮らしています。
カニューレ交換のときは、痛さと不安で毎回笑えないです。
日々介助者と訪問看護師に医療ケアを受けて暮らしています。
振り返ってみれば、機能低下を認められず過ごした日もありました。
でも、友だちに励まされ支えられ、仲間にめぐり逢い今日に至っています。
健常者でも体力の衰えを認めたくないと言っていたので、私だけじゃないんだと思う毎日です。
新しい年になってこんなことを書くのはなんだかなと思いましたが、自分のことを自分で認めるっていうのは難しいことだなと思ったので書きました。
「暮らしの支援」 理事長 鶴岡和代
2025-01-10
寒くなりました。みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
2024年はみなさまに支えられて、スタッフ一同頑張ってきました。
2025年もスタッフ一同みなさんに支えられてよき支援を行っていけるよう、努力していきたいと思います。
先月号でも書いたように、TSTを立ち上げた頃やっと障がい者の介護制度が作られて事業所経由で派遣をするようになりました。
高齢者の介護制度も介護保険制度になり、新しいかたちとなりました。
私たち障がいを持っている者も新しい制度になり、新しい暮らしや生活スタイルに根付いた制度となりました。
まだまだ介助の必要性が理解してもらえず、本当の介助時間が支給されないのが現実です。
今はどういう暮らしをしたいのか、介助がないとどう困るのか、そして社会とどう関わっていきたいのかなどなどはっきり伝えないと支給されない状況です。
それでも区によって支給量が違うのでなかなか難しいです。
支援する側もその人に合った介助を考えたりその人の希望を取り入れて支援したいと思っても難しいのです。
支援者に対して保障というものがまだまだ足りない状況で国会中継を聞いていると、私たちの訪問介護は議論されているようで、どういう観点で支給量が増えていくのか分からない話になっています。
TSTも一人一人の利用者に合った自立支援を行っていきたいという思いはあっても支援者の保障がないと続きません。
2025年は自立支援とはなにか、そして個別の支援とはどうあるべきかみんなで議論してみんなでもっともっと楽しい暮らしができるよう願っています。
願うだけではだめなので、支援者と共に自立生活運動を展開していかなければなりません。
とてもエネルギーが要ることです。
「未来へつなげる」 理事長 鶴岡和代
2024-12-01
11月に入ってやっと冬らしい気温になりました。
暖房を入れたり冷房を入れたりその日の気温によって温度調節が難しいです。
みなさんはいかがでしょうか。
さて、先月もちらっと支援と保障について書きましたが、私たちの暮らしは政治の行方によって色々なことが決まるので今回の政治の在り方もどうなることか、不安になります。
兎角、福祉は後回しにされやすいので、私たちが伝えていかないと今の暮らしは続きません。
TSTは、現在の私のように人工呼吸器をつけても生きていける、楽しいことも遊びにいくこともできる暮らしを夢見て団体を立ち上げました。
ただ、介助者のみなさんからしたら、まだまだ自分の暮らし保障はされていないと思うことでしょう。
それについては、国が福祉というものを見直すという考えを持たないと難しい問題です。
平成14年までは障がい者の介助制度が高齢者と一緒だったので、私たちが訴えても難しい状態でした。
福祉に力を入れて制度を整えていくと言っている国会議員もいるけど、少人数だと引き上げが難しいのです。
ただ、私たちの支援は、当たり前に暮らし当たり前に人として楽しみたい、それが叶う社会はまだまだ遠い。
みんなで声を上げていかないと、自民党が今回の選挙で少ない人数になったため、持ち上げるのがとっても難しいと思う今日この頃です。
11月は酉の市も3回やって、みなさんとお会いできるのを楽しみししています。