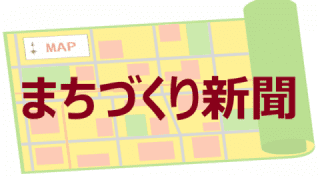理事長鶴岡 近況報告
桃の花 あずさやかいじで 往復し
自立に向けて 制度交渉し
むらさき(2025年3月)
「未来に向かう」 理事長 鶴岡和代
2024-01-01
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。
2023年はお世話になり、ありがとうございました。
ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
さて、2023年は感染症のコロナが5月くらいから第5類になって、マスクも個人個人で考えて外して外出する機会もあると思います。
それに伴って、コロナになった方もいて色々な後遺症が残って今でも苦しんでいるようなニュースも流れています。
TSTの皆さんは元気に過ごしていると聞いているので、嬉しく思っています。
2024年はどのような年になるのでしょうか。
政治の問題もあり、政治が変わると福祉にも影響が及びます。
そうならない為にも私たちが声をあげて必要なことを伝えていかなければなりません。
福祉はまとめられた内容になっていくほうが早いので、私たちのように一人暮らしでヘルパーがいて生活していくことがこの先もできるのか否か。
ニュースを見ていると見方によっては希望があり、一方ではグループホームのように何人かで暮らす方向になっていくという見解もありました。
本当に私たちの声を伝えていかなければならないと思う今日この頃です。
2024年が始まるので、未来に繋げていきましょう。
スタッフ一同皆で一緒に楽しく暮らしていく気持ちは強く持っているので、応援よろしくお願いいたします。
「笑顔集う」 理事長 鶴岡和代
2023-12-01
今日は11月10日です。
今月は浅草酉の市があります。
11日が一の酉で23日が二の酉です。
この通信がお手元に届くときには酉の市も終わっています。
11日が一の酉で23日が二の酉です。
この通信がお手元に届くときには酉の市も終わっています。
今年はやっとコロナも5類になってCILたいとうの集う場を設けようと思っています。
本当は居酒屋をやりたかったけど、まだまだ感染もなくなっていないのでちょっと方向性を変えてCILたいとうの年表を作って楽しんでもらえたらと嬉しいです。
たいとう名物の豚汁とおにぎりやサラダ、飲み物を提供して笑顔が集う場ができればいいなと思っています。
たいとう名物の豚汁とおにぎりやサラダ、飲み物を提供して笑顔が集う場ができればいいなと思っています。
ただ、居酒屋をやっていたときのように大勢の人に声をかけると事務所が密になってしまうので、声をかけられていない人もいっぱいいます。
来年の酉の市のときにはもっと多くの人に声をかけられたらいいなと願っています。
このホームページを見て、声をかけてもらえなかったなと思った人は申し訳ありません。
来年はぜひお会いしたいと思います。
今年の酉の市の内容が面白かったか、教えてもらえたらとても嬉しいです。
「介護者の保障」 理事長 鶴岡和代
2023-11-01
10月になっても30℃を超える暑さがありました。
今日は10月13日です。やっと涼しくなったような感じがします。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
熱中症やコロナ、インフルエンザになりかけた人もテレビで色々報道されていました。
私は特に変わったこともなく、元気で過ごしています。
今日は10月13日です。やっと涼しくなったような感じがします。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
熱中症やコロナ、インフルエンザになりかけた人もテレビで色々報道されていました。
私は特に変わったこともなく、元気で過ごしています。
さて、2回に渡って自立生活の師匠である新田さんのことを書いてきました。
前回、『愛雪』のことを書きましたが、Amazonで購入した人もいたようです。
私にとって新田さんという師匠は介護制度のない時代から介護制度を作っていく仕組みを教えてくれた人です。
新田さんにとって自立生活センターというものは介護制度があってこそという考えでした。
介護制度が少ない中でセンターを作ったら自分の介護も難しくなるよと言われて、私がCILたいとうを作るときも反対されました。
当時、私は専従介護人という私と個人で契約して色々な介護制度組み合わせて介護をしてもらっていました。
新田さんが東京都や厚生省と介護制度の交渉をしていたのは介護者の保障をするためでした。
支援費制度になってセンターが必要となり、専従介護人をお願いしている人の保険の保障をするために新田さんと一緒になって仲間に入れてもらいました。
介護者の保障は介護制度が高まらないと難しいことです。
支援費制度になる前は本当に毎日が交渉の闘いで、正月から厚生省と制度交渉をしている夢を見て目が覚めたらベッドの上だったという笑い話もあります。
介護制度が少ない中でセンターを作ったら自分の介護も難しくなるよと言われて、私がCILたいとうを作るときも反対されました。
当時、私は専従介護人という私と個人で契約して色々な介護制度組み合わせて介護をしてもらっていました。
新田さんが東京都や厚生省と介護制度の交渉をしていたのは介護者の保障をするためでした。
支援費制度になってセンターが必要となり、専従介護人をお願いしている人の保険の保障をするために新田さんと一緒になって仲間に入れてもらいました。
介護者の保障は介護制度が高まらないと難しいことです。
支援費制度になる前は本当に毎日が交渉の闘いで、正月から厚生省と制度交渉をしている夢を見て目が覚めたらベッドの上だったという笑い話もあります。
今現在、一人ひとりに必要な介護制度が認められている自治体もあれば、必要なのに認められていない自治体もあります。
これからも新田さんが闘っていた介護制度は私たちにとっても闘いです。
私たちも介護者のみなさんも障がい者の介護制度及び福祉制度は闘っていかないと政治が衰えていくと同時に保障も少なくなってしまいます。
みなさんには何を言っているのか分からないのかもしれませんが、30年前に介護制度は闘わないと伸びていかない時代でした。
私の想いや熱ばかり高まってしまってこんな文章になりました。
これからも新田さんが闘っていた介護制度は私たちにとっても闘いです。
私たちも介護者のみなさんも障がい者の介護制度及び福祉制度は闘っていかないと政治が衰えていくと同時に保障も少なくなってしまいます。
みなさんには何を言っているのか分からないのかもしれませんが、30年前に介護制度は闘わないと伸びていかない時代でした。
私の想いや熱ばかり高まってしまってこんな文章になりました。
聴きたい方は鶴岡まで、聞いてください。
「毎日が学び」 理事長 鶴岡和代
2023-10-01
9月になっても猛暑続きの毎日と台風が何回も来て外回りの介助者は大変だと思います。
訪問看護の看護師も雨の中大変だと言っていました。
気圧によって体調が変化する人もいると思います。
みなさんは体調は大丈夫でしょうか。
さて、前回に続き、自立生活の色んなことを教えてくれた師匠についてお話します。
師匠は男性で健常者の人と結婚していて子どももいました。
その頃は小学生だったと思いますが、子どもさんを学童に迎えに行ったりするのを私もついて行ったりしていました。
障がいがあってもお父さんとして子育てに関わるんだなと思ってびっくりしたのを覚えています。
介助者との関係も師匠は喜怒哀楽を表して自分の感情を伝えていました。
きつい言葉で言ったりすることもあるけれど、そのあとは笑ってその場を和ませていました。
私も介助者と行き詰まっちゃうことがありますが、師匠のようにその場を和ますことは未だもってできていないです。
私の場合は、喜怒哀楽を表すのがどうしても言葉を言うだけになっちゃって雰囲気を和らげるまでいかないです。
毎日悩んだり、ときには悲しくなったりすることもあります。
当時、自立生活センターはなかったけど、師匠や周りの先輩方に色々教わって自分なりに学んできました。
昭和の時代と令和の時代の今は福祉制度の違いがあり、難しいなと思う時があります。
自立生活センターたいとうは25年くらい経っているけれど、なかなか私がしっかりしないこともあって頑張らなきゃなと最近思っています。
自立生活センターたいとうにも置いてある新田勲の『愛雪――ある全身性重度障害者のいのちの物語』という本があります。
それを読むと私が伝えていることが少しは分かると思います。
みなさんもぜひ読んでみてください。
「師匠に感謝」 理事長 鶴岡和代
2023-09-01
7月・8月毎日暑い日が続いていて熱中症が心配です。みなさんお元気でしょうか。
私のことを知りたい介助者が多くて、「つるさんが自立した頃って自立生活センターはあったのでしょうか」と聞かれました。
私が自立したのは平成2年です。
その頃は自立生活センターも少なくて、台東区には設立できていない状態でした。
私には自立生活を色々教わる先輩がいました。麦の家という入居施設にいた頃にであった先輩です。
その人は府中療育センターという施設に入っていたときにものすごくひどい扱いをされて、座り込みの運動までやって自立生活をした人です。
昭和62年に全国介護制度運動というのがあって、そこで出会いました。
言葉も喋れず、足文字で介助者に読み取ってもらって役人に伝えていました。ものすごく衝撃だったのを覚えています。
そして私も麦の家を出て自立生活をしたいと思い、その人が北区に住んでいたので毎日通って勉強をしました。
私にとってその人は自立生活の師匠です。
毎日通っても何も教えてくれなくて、どうしたらいいか分かりませんでした。
もう帰ろうと思って「お邪魔しました」って言ったら「ラーメン食べるか」って言われて「いただきます」と返したら、師匠が介助者に足文字で作り方を教えて美味しいラーメンが出来上がりました。
こうやって介助者とやりとりをするんだとすごく勉強になりました。
制度交渉の運動のことも足文字で介助者に伝えて交渉文を作っていました。
私は訳が分からず呆然としながらそのやりとりを見ていて制度交渉のとき介助者が読み上げ、障がい者の実情をものすごいパワーで伝えていたのをいまでもはっきり覚えています。
その師匠のおかげで台東区や東京都とも交渉し、厚生省にも交渉のため座り込みをすることもありました。
そうした自立生活の運動があってこそ、今の暮らしがあります。
平成2年の頃は24時間介助を入れていたけど、90%がボランティアでした。
今もまだまだ金額的には低いけど、介助者として暮らしが成り立つようになりました。
師匠は10年前に天国に旅立ったけど、私の中では今でも生き続けています。
みなさんも自立するときに色々と学んだ人がいると思います。
自立生活センターたいとうは平成8年に設立したので、なかなか思うように自立のサポートができませんでした。
介護制度もまだまだ不十分だけど、今に至ったのはその師匠と先輩方のおかげです。
今回はこの辺で…。