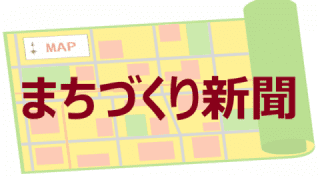理事長鶴岡 近況報告
桃の花 あずさやかいじで 往復し
自立に向けて 制度交渉し
むらさき(2025年3月)
理事長鶴岡の近況報告(10) 副理事長 宮尾正基
2018-12-25
「鶴岡さんの在宅生活はこれでいいのか!?」という声が少なからずあがってきている。
本人がこうしたい(外に出たくない!)って云ってるんだから、まったく余計なお世話なのだろうが、
で、少しでも繋がりをつけようと、これもまた余計なお世話なんだろうけど、
で、少しでも繋がりをつけようと、これもまた余計なお世話なんだろうけど、
鶴岡さんに会いたい!と云う人達を積極的にコーディネートし始めた。
CILたいとうメンバーに始まり、
8/17 関係団体のNさん
9/21 利用者のFさん
11/16 元介助者のHさんとWさん
12/17 利用者のKさん などなど
8/17 関係団体のNさん
9/21 利用者のFさん
11/16 元介助者のHさんとWさん
12/17 利用者のKさん などなど
毎回、「邂逅」という表現が良く似合う素敵な時間に感じる。
まぁ、鶴岡さんにとっては疲れる方が多いのかな(苦笑)
これもまた余計なお世話かなぁ(苦笑)
そんな、相変わらずの自問自答を少しでも払拭しようと、
昔から知っていて(介助をしていた)
「CIL北」の理事長であり「呼ネット」の代表でもある気管切開当事者(変な表現!?)
Oさんに11/20相談に行ってみた。
相変わらず終始笑顔の穏やかな方で、お忙しい中1時間30分もの間、
相変わらず終始笑顔の穏やかな方で、お忙しい中1時間30分もの間、
そんじょそこらの講習会なんぞ足元にも及ばない程の良いお話を聞けた!!
自然に痰吸引を目の前でされたり、さらりと「最近あんまり家にいないんですよ」と笑いながら話したり、
自然に痰吸引を目の前でされたり、さらりと「最近あんまり家にいないんですよ」と笑いながら話したり、
目から鱗のオンパレード!!
「僕も当時は気管切開してまで…って思いましたよ」
「医師はあれダメこれダメばかり」
「僕も何年かは引きこもりでしたよ(笑)」
「昔は外に出れるなんて考えもしなかったですよ」
「僕も当時は気管切開してまで…って思いましたよ」
「医師はあれダメこれダメばかり」
「僕も何年かは引きこもりでしたよ(笑)」
「昔は外に出れるなんて考えもしなかったですよ」
なるほど!なるほど!
「周りは皆いろいろ云うんですけど、当時はただうるさいなぁ~としか思えなかった」
ガーン!!
「きっかけだったんですよね! そういうタイミングが偶然いろいろと揃ったんですよ。
そして丁度その時に背中を押してくれた人(介助者)がいたのがきっかけでしたね。いまこうなったのは!
それまで3~4年かかりましたよ(笑)」
まさに、ガーン!!!!
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(9) 副理事長 宮尾正基
2018-11-20
先日、KST(「要を支える会」という個人への支援グループ)と「CILたいとう」との合同企画により
「幸せのありか」というポーランド映画の上映会を行った。
試みとしてはなかなか良かったはずなのだが、蓋を開けてみればアナウンス不足なのか?
動員数は哀しいものだった…(苦笑) またいつかリベンジかなぁ…(汗)
映画を観て、その内容だけでなく、自分や周囲を見渡した時に感じる
「地域でのそれぞれの暮らし方に於いてのそれぞれの幸せのありかへの模索」がテーマ。
例えば、鶴岡サンを支援するにあたって、とか。
「話を最後まで聞きなさい!」
「まだ話は途中です。○までちゃんと聞いてから動きなさい!」
永年鶴岡サンと共に、言語障がいがある方々への聞き取り姿勢として、上記フレーズを用い、
初めて介助をする人達や地域の人達へことあるごとに口を酸っぱくして云ってきた。
今、鶴岡サンの言語は、昔とは比べものにならない位聞き取りづらい。
いや、正確に云えば、一般的な定義での言葉ではないのかも知れない。
一番聞き取りが上手なスタッフでも完全ではないと思う。
おそらく、「口から出る言葉に近い音」と「口の動きを見て」のその二つを重ね、
それらに「現状で云いそうな事」「鶴岡さんが云いそうな事」を加えた「予想」「予測」なのだと思う。
それは、従来我々が「予想で聞いちゃダメ! 予測で動いちゃダメ~!」と散々云ってきたこと、とも云える。
それを今やってしまっている、とも云える。
でも、そうじゃなきゃ、もう事がまわらない…。
しかも、鶴岡サンは本来、いろいろな注釈やら鶴岡流言い回しやらが加わる話が長い人だった(笑)から、
きっと今はなかなか聞き取れないであろう我々のことを気遣って、
かなりシンプルな伝え方で話してるんだろうなぁ、と思う。
でも、それでも分かりづらい、なんて!
鶴岡さんとは、共に昔から心理学を学んできた。
カールロジャースのクライアント中心療法という流派を。
おそらくそれがたいとうの支援指針の下地になっているのだと思っている。
共に学んできた学びの中で一番重きを置いていたポイントが「聴く」ということ。
それをとことん考えていた。
言葉だけじゃない相手が云いたいことへの感じ方を「聴く」、
そしてそれを「聴く」時の自分の感じ方(フォーカシング等)は?
とかを考える。
そして「聴く」と「聞く」の違いとは何なのか?を掘り下げて考える…などなど。
鶴岡サンは、その頃の学びを今の原状と照らし合わせ、どう思ってるのだろうか。
個人的には、我々支援者は非言語コミュニケーションの領域を考えねば、と思っている。
それが今後の支援指針の矛先なのかもしれない。
いや、まてよ!? それって、実は、昔からも必要だったことだったのでは!?
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(8) 副理事長 宮尾正基
2018-10-22
淡々と、穏やかな日々が続いています。とても良い事です。
変化や進化があることだけが幸せではなく、
こうしてなんでもない日常が昨日・今日・明日と着実に続く事こそが
幸せなのかも知れない…。
しかし!
台東区はイベントが多い街、当法人もイベントが多い団体、
「酉の市」「クリスマス」「年末年始」…と季節はこれからは特に!
そして、そもそも地域での自立生活って運動の繰り返し・積み重ね、なのに…
まぁ、今は、まだ軌道に乗ることが最重要なのかぁ…。
気切(気管切開)の方でも新幹線や飛行機に乗って全国各地をとび回ってる方や、
夜の屋台でレモンサワーを美味そうに呑む方とかもいるのになぁ~!
それって、本人とモチベーションなのか!? 介助者の支援の見せ所なのか!?
う~ん…。
と、それはおいといて、
ここらで、「ターミナルケア」「終末期介護」「看取り介護」について、
改めてちゃんと考えてみたい。
設立当初から、「たいとうが死ぬまで支えますよ!」とか「たいとうにさいごまで支えて欲しい!」とか
云ったり云われたりしているけど、それって、実際、どうゆう意味なのか!?
まさに鶴岡さんの件で、これかぁ~という場面が何度かあった。
「本人」の意向は勿論、「家族の意向」そして「主治医の立場」からの明確なやり取りが生じ交差する。
それは、「将来的~して欲しい」という緩いやり取りではなく、
もっとリアルに「今度~の状態になったらどうしますか?」というかなり緊張感高いやりとり。
そのやりとりの結果如何では、介助者としてどこまでやっていいのか? への制限がひかれることにもなる。
「え!?じゃぁ我々介助者は何にも出来ないんですかぁ!」「手を握ってるしか出来ないんですかぁ!」とか
主治医に強いレスポンスをしてしまってたけど…。
医療と福祉の連携ってこうゆう場面なのかぁ…。
「ターミナルケア」「終末期介護」「看取り介護」の正確な意味は、此処では敢えて表記しません。
是非、みなさん自身で調べて「へぇ~!」と実感してみて下さい。
その上で、「たいとうが死ぬまで支えますよ!」とか「たいとうにさいごまで支えて欲しい!」
とかいう意味を深く考え、それでも同じフレーズを云ったり云われたりたいです!
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(7) 副理事長 宮尾正基
2018-09-19
鶴岡さんが戻ってきて、鶴岡さんがいる日常に、だいぶ慣れてきた。←妙な表現だが…
医ケア(医寮的ケア)研修もずいぶん起動に乗ってきたようで(訪看の皆さんには感謝しきれません!)
支援体制も安定し、今のところ大きなトラブルはない。
でも、
未だに自宅(REENA)の中だ。
未だにベットの上だ。
訪問客もチラホラくるようになった。
皆、
「良かったね!」
「思ったより元気!」と云っている。
う~ん、、、頭を過ぎる或る想い…。
やはり、
「外に出て欲しい」と思ってしまう。
――これって支援側のエゴだろうか!?
やはり、
「地域でガンガン鶴岡さんらしく楽しんで、周囲の度肝を抜いて欲しい」と思ってしまう。
――これって支援側のエゴだろうか!?
「病床と何が違うのか?」 「病院よりも圧倒的な個別対応、手厚い介助(本人の希望通りの痰吸引や体交換)が受けられてるだけの違い?」――この見解ってオカシイ!?
天井とテレビを観ているだけの鶴岡サン…。
外に出るのは想像以上に体がきついんでしょうね…。
なかなか周囲に伝わらないから、口数が減ったんですかね…。
あんなにおしゃべりな人だったのに…。
「昔は夜中まで、秋葉原とかで一緒に呑んだじゃないですか~」
「一緒にミュージカルとかいろいろ観に行ったじゃないですか~」
「外に出す」というのはおかしい…。
『外に出たい!』と想って欲しい。
『○○に行きたいから、宮尾、なんとかしろ!』と、あの昔みたいな下町口調で云って欲しい。
ねぇ、皆さん、、、どう想います!?
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(6) 副理事長 宮尾正基
2018-08-27
鶴岡さんが自宅に戻ってきてから「約2ヶ月」が経つ。
ADLレベルの日々の支援は、何とか、かなぁ…という感じになってきた。
ADLレベルの日々の支援は、何とか、かなぁ…という感じになってきた。
さて、これからが我々支援者たちの真価が問われる!
「生命維持」なのか? 「自分らしい暮らし」なのか?
そもそも「生命維持どまり」の支援ならば、極論、在宅よりは病院の方が安全。何故?それを在宅(医療的視点から見れば極めて危険な)に移行したのか?
本人が望んでたから? 支援者はそのスタンスだけではもう足りない! 本人主体とは一見聞こえがいいが、時として支援者として無関与ということにもなる。それではあまりにも無責任! ※「生命維持」自体の考えを否定しているわけではありません。
「生命維持」なのか? 「自分らしい暮らし」なのか?
そもそも「生命維持どまり」の支援ならば、極論、在宅よりは病院の方が安全。何故?それを在宅(医療的視点から見れば極めて危険な)に移行したのか?
本人が望んでたから? 支援者はそのスタンスだけではもう足りない! 本人主体とは一見聞こえがいいが、時として支援者として無関与ということにもなる。それではあまりにも無責任! ※「生命維持」自体の考えを否定しているわけではありません。
今こそ考えなくては! 我々がやっていることの本質を!
地域支援って何?
鶴岡さんは昔から口癖のように云っていた。「施設は絶対嫌だ! 自分らしく地域で暮らしたい!3日生きれればいいから」と。
今の鶴岡さんは、昔みたいに流暢には話せなくなってしまった。
鶴岡さんは、今何を云いたいのだろう?
あんなお喋りな鶴岡さんがさぞやもどかしいだろう…。
「私は人前で喋るのが大好きなんだよ! 話す相手の数が多ければ多いほど燃えるね~!」
我々支援者は、何を汲み取ればいいのだろうか!?
鶴岡さんの負? それも必要だけど、その感情だけに付き合ってばかりいては前には進めない!
生きる悦びを提供出来ないだろうか!?
今の鶴岡さんは、昔みたいに流暢には話せなくなってしまった。
鶴岡さんは、今何を云いたいのだろう?
あんなお喋りな鶴岡さんがさぞやもどかしいだろう…。
「私は人前で喋るのが大好きなんだよ! 話す相手の数が多ければ多いほど燃えるね~!」
我々支援者は、何を汲み取ればいいのだろうか!?
鶴岡さんの負? それも必要だけど、その感情だけに付き合ってばかりいては前には進めない!
生きる悦びを提供出来ないだろうか!?
支援者は今こそ考えよう!
QOL? いやいやもっとその先へ! 在宅福祉は進化せよ!!
QOL? いやいやもっとその先へ! 在宅福祉は進化せよ!!
PS
緊急時用に、自分も鶴岡さんの医療ケア(痰吸引や経官栄養)対応が出来るように、資格取得し現在実地研修をしている。
これまでの介助と違うその緊張感を体感し、リアルに気を引き締めている!
緊急時用に、自分も鶴岡さんの医療ケア(痰吸引や経官栄養)対応が出来るように、資格取得し現在実地研修をしている。
これまでの介助と違うその緊張感を体感し、リアルに気を引き締めている!
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。