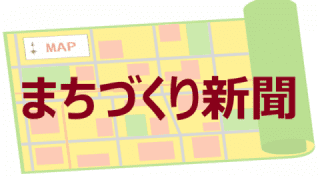理事長鶴岡 近況報告
桃の花 あずさやかいじで 往復し
自立に向けて 制度交渉し
むらさき(2025年3月)
理事長鶴岡の近況報告(20) 副理事長 宮尾正基
2019-10-21
今、鶴岡さんが熱い!!
まず‘食’への意欲 が凄い!
え!?‘食’!? 気管切開じゃないの!?
と思うでしょう?
そ~なんです! 謎 なんです…
なぜ口から…!? なぜ飲み込めるの…!? と…。
それは「お粥」に始まり、「そうめん」「トマト」「温玉」、そして「(介助用)すきやき」…
「葡萄」は断念したそうですが、まさに謎!というか…もう驚愕!
医学でも説明がつきにくいみたい…。
現在STの方のみで食事を摂っていますが、介助者でも出来るように!が目標
…というか、もはや、なにそれ!?って領域!!
車椅子に座っての食事みたいで、
え!?それってもはや完全復活じゃん!?
いやはや…
で、それだけにとどまらず、
「酉の市の女将」は勿論のこと、「スカイプとかが整備されれば会議も参加するよ」と。
そして、なんと! 遂に!
「舟木一夫のコンサートに行きたい!!」 という
待ちに待ったフレーズが!!
早速、チケットゲット!!
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(19) 副理事長 宮尾正基
2019-09-20
先日の台風15号の爪跡は大きく、未だに多くの方々が困難を強いられているようです。
無論、福祉関連現場でも同様で、
今回特に停電により、自宅で人工呼吸器が使えないという自体が起こったようです。
そして、「発電機」の必要性が急浮上してきました。
我々も、何度か「発電機を持つ」という話は持ちあがってはいたのですが、
“いやぁ~そこまでは…”と決めずじまい…。
しかし、今回ばかりは…!
で、補助でも自費でも、近日中にREENAに設置する方向で進めています!!
皮肉にも、教訓とは、かなりの犠牲により切迫化するものなのですかね…。
さて、鶴岡さんは、経鼻官栄養から胃ロウに無事変更となり、元気です!!
元気すぎて、また何かいろいろ企んでるようですが…(笑)
そろそろ生活も軌道に乗って来たようなので、
また、地域支援の担い手として一緒にいろいろやりましょう!
と、こちらも企んでます(笑)
ふと思ったのですが、何となく、医ケア(医療的ケア)は、
かつて全身性(※)がまだまだ認知度を獲得していなかったあの頃の匂いに似ている。
やればやるほど、埃も出るが、どんどん体系化が進む。
医療関係者や他相談員が「この団体、やれるんだぁ…」と分かると
たちまちその情報が拡がり問い合わせが増える。
病院によってはこれまでの「医ケア=そこで永住」の図式が崩れることにも繋がる。
おそらく数年で利用者数が急増し、ニュースタンダードになるのは間違いないと思っている。
そう、かつての全身性のように。
※「全身性介護人派遣制度」
それだから、今後、我々支援者は、
医療側を牽引するぐらいの気構えと実績をつけていかねばならない。
そして、その支援者としての高い意識と実績が医ケアではない方々へも活かされる、
という素晴らしい循環構図を創りだせるに違いない!
そんな話を鶴岡さんと今度詰めなければ! 「ですよね!?」
※気が付けば、TSTの医ケア利用者は5名(男性3名2名)になりました。
さらに、他に何名かのオファーも来ています。
医ケアは、まず追加の座学講習会(&続いて実技も)が必要です。
これまでは、或る団体へその都度依頼していたのですが、
ここまで増えると日程調整等がかなり困難になってきました…。
そろそろ自前で講習会をしなくては…と考えてます。
(現在は、CILで、重度訪問介護・移動支援(墨田)の開催が可能)
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(18) 副理事長 宮尾正基
2019-08-20
コンプライアンス
いつだったか、何気に眺めていたTVでオシャレなコメンテーターが
「Complianceするのが~」 とか言って難しいことをベラベラと語っていた。
カッチョいい響きの言葉だなぁと思い、どういう意味だろう?と、ググッてみた。
…、ふ~ん…。
当方人は、障がい者児の地域支援を行なう為に設立した。
当方人が云うその支援とは、必ずしも「行政機関へ事業申請した内容通り・杓子定規の福祉」ではなく、
「支給決定された範囲内」だけに甘んじるでもない
『もしもその支援が現存しなく、それでもその支援が必要ならば創り出してでもやる』、である。
「死ぬまで支援」「骨を拾う」なんて、これまで場面によって云ったりしてきたけど、実際そういう場面はまだほぼない。
鶴岡さんの病院で行われたやり取りの中で、その意味をリアルに想像させられ、自問自答させられる場面が何度かあった。
その、大袈裟ではなく、一瞬鋭い何かが背筋をサッと走るような感覚、その温度感を皆さんにも少しでも伝えたい。
もっと細かいことを書きたいが、こればかりはいろいろ難しいので書けないが、
我々は、これからこのレベルの支援を行っているのだ、とだけ伝えたい。
命の軌道を任せられた、と。
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(17) 副理事長 宮尾正基
2019-07-20
先日「経鼻官栄養」から「胃ロウ」に変更することを決断した鶴岡さん、、、
手術を控えた今(本文作成時)、この機会に、入院時介助の実態について報告を!
平成30年4月付けで、東京都の要綱にて重度訪問介護の入院時対応が可能となった。
本人の支援としては、勿論だが、
介助者の保障(自分が普段関わっている利用者が入院すると介助=仕事がなくなる)
としても永年の悲願が遂に~!
なのだが、その実態はまだまだ認知度が低い茨の道である…
↓
●各区役所の障害福祉課にて
重度訪問介護の入院時での原則的な内容は「コミュニケーション支援」となるのだが、
各区により規定が微妙に違う。
例えば台東区は「コミュニケーション支援」
例えば江東区は「コミュニケーション支援、等」
北区はメッチャ細かい…(苦笑)
何れにせよOKになったのという事は大変喜ばしいのだが、
↓
●他法律とのミックス
介護保険では在り得ない概念であるが、
65歳を過ぎると優先法律として介護保険がまず適応される構図になる。
→実際そうなった鶴岡さんの例
まず障害福祉課に入院時介助の申請に行くと、介護保険課にまわされた。
介護保険課では即答で「無理です」と。
再び障害福祉課に戻りその旨話すと
「介護保険適応者に対しての障害制度はあくまで介護保険の補填でしかない。
介護保険上で介護が認められない場合はそもそも補填にはならならないから無折理です」
と(怒り!)
→その後の展開は、、、
↓
●病院にて
上記を経て、ではいざ病院へ、、、しかしこれがまた茨の道そのもの、、、
病院側「は?何ですか?」「こちらが全部やりますから」「面会ってことですか?」
結局、「他の入院されている方々との兼ね合いもありますので面会ってことなら」
「あ!あまり勝手なことはしないで下さいね。何かあったらこちらの責任ですから」と、、、
→「個室ならいいのか?」と聞くと、病院側は「まぁ」と、、、
↓
●プラス、生活保護受給者は厳しい
ケースワーカーが認めない。「個室はちょっと、、、医師がどうしても必要と云うなら、、、」と。
え~!? 医師がどうしても必要か?だって? それは、、、(絶句)
→完全自費? いやいや、そもそも生活保護受給者なんで、、、
などなど ん~、、、まだまだ茨の道だ、、、でも切り拓きましょう!!
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。
理事長鶴岡の近況報告(16) 副理事長 宮尾正基
2019-06-25
鶴岡さんが三社祭を観に行った!!
に続いて、今度はなんと、事務所(理事会・総会)にキタ~!!
僅か40分程の時間だったけど、その光景は、何というか、感動的ですらあった!!
前回(理事会・総会)は「スカイプ」参加で、まぁそれでもいいんんだけど、
あぁ~今後はこの形が定着しちゃうんだろうなぁ~なんて思ったりもしてたから、
見事にその予想を裏切ってくれたのは爽快であった!!
鶴岡さんが事務所にいると、やはり、場がシマルというか、「在るべき絵」になる感じだ!!
いいね~! やっぱり!!
(三社祭も)実は最初本人は外に出るのに気が重かったらしい。
おそらく体の痛み等の不安が気を重くさせていたのだろう。
そんな鶴岡さんの重い腰!?を動かす決め手となったのは、
やはり、介助者や訪看さん等周りの関係者の素晴らしい後押し!!
「行きましょうよ!」
「大丈夫ですよ! 私たちが付いてますから!」
最近痛切に思う。
我々支援者が動かなければ何も変わらないことが多い。
私達が長年大切にしてきた「自己決定」だけでは、時には何も進まないこともある。
その答えをモロに見た感じだった。
これからは、『前向きな自己決定が出来る支援』が大切なんだ、きっと!!
だって、『外の風を浴びたいから歩いて事務所に行こう!』なんて鶴岡さんに言わさせちゃう支援
なんて最高ジャン!!
さ~て、そろそろいろいろ忙しくなりそうだぞ~!!
あの超アクティブな鶴岡さんが帰ってきそうだ!!
また呑みに付き合わされる日が来るのも、そう遠くなさそうかな(苦笑)
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。