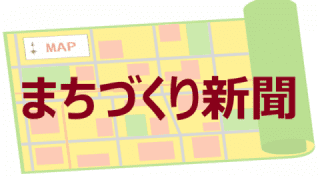理事長鶴岡 近況報告
理事長鶴岡の近況報告(13) 副理事長 宮尾正基
2019-03-25
一昔前は、脳性麻痺の方々が重度と云われてきた。
今は、気づけば重複障がいの方々が多くなってきている。
そして医療的ケアへ。
「脳性麻痺者への理解」「重度障がい者の支援」を自らを媒介とし牽引してきた鶴岡サン。
今は「医療的ケアの安定」「ターミナルケアの真意」という支援最先端を実践しているのかも知れない。
かつて脳性麻痺の方々が唱えた、「本人主体」「自己決定自己責任」というコンセプトが自立生活を具現化し、
制度拡大になっていった。
介助者は、「指示待ち」「確認」の姿勢が問われるというそれまでとは全く違った支援スタイルを求められ、
カルチャーショックともいえる衝撃を覚えたものだ。
そしてそれが新しい支援スタイルを生み出していった
しかし本人からの指示が組み取りにくい方々が増え、
無論その方々の支援に於いても「本人主体」「自己決定自己責任」を当てはめているのだが、正直難しい実情が多々ある。
介助者は、「指示待ち」「確認」が出来にくい。
「指示待ち」「確認」を培ってきた介助者は当惑し始めた。
そして医療的ケアは、どうだろう…。
かつて脳性麻痺の方々への支援は、或る意味で介助者の経験値やスキルが邪魔する場合があった。
寧ろ未経験の方が良かった場合も少なくない。
しかし、重複障がいの方々への支援または医療的ケアは、まさに介助者の経験値やスキルが活きる。
例えば痰の吸引などは、一回の介助で3~4回、それを週2~3回常時経験し続ける位ならばかなり慣れ技術も上達する。
前職が施設などでの医療的ケア経験者だと無論ダントツに習得が早い。
しかし、週に1回あるかないかという頻度だと毎回めちゃくちゃ緊張する。
そして技術はなかなか進歩が遅く、利用者は怖いだろうし不快を与えているのだと思う。
例えるならば車の運転みたいなものだろうか。
こればっかりは、「利用者も介助者を共に育成して欲しいからしばらく成長を見守って下さい」というには限度がある。
やはり我々介助者が自らスキルをしかもなるべく早期に上げなくてはいけないし、
事業所としても前述したようにスキルが上がる関わりの環境を築いてあげなくてはいけない。
医療的ケアと云えば、云うまでもなく医療機関とかなり密なやり取りが生じる。
そういった場面に於いても介助者及び事業所の経験値が浅いと困る場面が多い。
医療的ケアの経験値豊富な事業所と一緒になる他の現場があるのだが、
介助者が訪看さんにバンバン指示を出し対等かそれ以上に随時議論している。
なんか、とても頼もしい。我々もそうありたい。
だって、日々関わっている密度濃いのは医師や訪看さんではなく我々介助者なんだから、
関わっている利用者のことは介助者が一番知っているはずだから!!
支援者・団体共にHI STANDARDを目指しましょう!!
※各コメントは、逐語ではなく多少装飾しています。